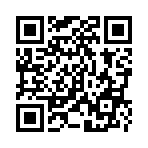2007年09月15日
ビルベリーの秘密(2)
□ ビルベリーの売りは
ビルベリーはヨーロッパで、
伝承薬として凡そ1000年に渡って使用されてきました。
でも用途としては、乾燥果実を煎じて、
下痢や赤痢の治療に用いられた、と言われています。
その後、長い経験的な背景により目に良いことが次第に認められ、
ドライバーやパイロットのような目を酷使する人たちや、
夜盲症の人たちに対して、
ビルベリー(ブルベリー)の摂取が薦められてきました。
今では、ビルベリーと言えば、目に良い健康食品と知られていますね。
新鮮なものを食べるのが一番ですが、
いつも決まった量を摂取するにはやっぱり健康食品が、
手軽な点で、摂取量のコントロールを行いやすい点で、一番です
2007年09月13日
ビルベリーの秘密(1)
□ ブルーベリーとビルベリー
最近、パソコンの仕事が増えていますが、
そうでなくても情報量の多い今日では、
目は疲れる一方です。
目に良い健康食品が欲しくなりますね。
ブルーベリーは目に良い、とずっと言われていますが、
なぜ、目に良いのでしょうか。
さて、その前に、ブルーベリーとビルベリーの違いをご存知でしょうか。
ブルーベリーはツツジ科の植物ですが、
栽培種を含めて多くの種類が存在します。
中でも有効成分が多いのは、
野生種のビルベリーと呼ばれる種類なのです。
ですから、健康食品をお求めの際には、
ビルベリーを原料にしたものがオススメです。

通常の食用ブルーベリー
ビルベリーは、樹高も低く、ベリーも小粒で、
収穫に手間がかかります。
有効成分は果皮に含まれますから、
小粒なほうが単位重量当りの含量が高くなります。
2007年09月08日
ゴマの力(7)
こんにちは
 その他のリグナン成分の生理活性
その他のリグナン成分の生理活性
セサミンというのはすごい化合物でした。
セサミンはリグナンの一種ですが、
ほかのリグナンにも、何らかの生理活性があるような気もします。
ゴマ油を製造途中で、セサモリンは酸化を受けてセサミノールに変換されてしまいます。
このセサミノールもまた、悪玉コレステロールであるLDL(低密度リポタンパク質)の酸化障害を強力に抑制することが分かったそうです。
しかもこのセサミノール、
ゴマの中では、一部、配糖体の形で存在していて(糖と結合した状態にあって)、
水溶性になっています。
これをゴマ油抽出後の残渣から上手く水抽出して、
セサミノール配糖体として取り出すと、
腸内で分解されて、生体内で抗酸化作用を示したそうです。
つまり、セサミノール配糖体はゴマ残渣という未利用資源の活用という意味だけではなく、
水溶性の抗酸化剤として魅力的ももっているのです。
今回でゴマのことは終わりです。
ゴマの活性成分セサミン
2007年09月02日
ゴマの力(6)
こんにちは
 セサミンの生理活性
セサミンの生理活性
セサミンを摂取すると、
体の中で優れた抗酸化物質として働いてくれるのですが、
これ以外にも、動物実験で次のことが分かってきたそうです。
- 小腸からのコレステロール吸収抑制
- 肝臓でのコレステロール生合成阻害による血清コレステロール低下作用
- アルコールの過剰摂取に起因した肝障害の抑制作用
- 坑高血圧作用
などです。
色々、ご利益がありますね。
しかも、セサミンの安全性には問題が無いことが証明されています。
次回もゴマのことについて書きます。
2007年09月01日
ゴマの力(5)
売れ筋の健康食品のご紹介をしています
 ゴマリグナンの働き
ゴマリグナンの働き
リグナンというのは、ある構造を持った化合物の総称です。
中には、どんな化合物が含まれているのでしょうか。
ゴマの種子は、油分が多い割には、長期保存ができ発芽率が落ちない、
ゴマ油は不飽和脂肪酸の油脂が多い割には、酸化されにくい、
という事実があります。
これは、リグナンやそれに関する類似した構造の化合物の働きと考えられています。
なんだか、体によいものが、リグナンとして入っていそうな気がしますね。
健康食品開発に繋がりそうです。
リグナン類は全体の1%程度しか含まれていませんが、この中には、セサミン、セサミノール、セサモリンなどが含まれています。
この中で活性が強く、最も研究されているのがセサミンです。
次回の「売れ筋健康食品 イチオシの理由」も、ゴマのことについて書いていきます。
ゴマの活性成分セサミン
2007年08月31日
ゴマの力(4)
こんにちは
 ゴマの成分は何?
ゴマの成分は何?
一般的なゴマの成分(ゴマ油)は、次のように言われています。
脂肪酸として、
不飽和脂肪酸であるオレイン酸、リノール酸、パルミチン産、ステアリン酸、
飽和脂肪酸であるパルミチン酸、ステアリン酸
が、脂肪油としてあり、45-50%を占めると言われています。
やっぱり、油分が多いですね。
ここで脂肪酸として、とあるのは、
実は色々な化合物と結びついて存在いるのだけど、
基本的な構造として分けると、という意味に理解しておいてください。
不飽和脂肪酸というのは、分子内に一個以上の2重結合をもった脂肪酸のことです。
これにフェノール性の化合物が重合した、リグナンという物質が1%程度存在します。
実は、これが大事なことが分かってきました。
後で書きますね。
これに加えて、ビタミンE、A、Bなどが豊富、と分析されています。
ゴマは体に良さそうですが、油分が多く、高カロリーであることが玉に瑕です。
何とか活性成分だけを取り出した健康食品があれば、手軽にゴマの恵を受け取ることができますね。
次回もゴマのことについて書きます。
ゴマの活性成分セサミン
2007年08月30日
ゴマの力(3)
こんにちは
 ゴマは万能薬?
ゴマは万能薬?
ゴマはどのように使用されてきたのでしょうか?
養分に富みますから、滋養強壮に用いられたことは間違い無さそうです。
中国では昔から、滋養強壮、粘滑、解毒効果があるとされ、虚弱体質の改善、病後の回復、便秘治療などに用いられてきたそうです。
ゴマ油は軟膏の基剤として使用され、やけどの優れた治療薬である「紫雲膏」にも入っています。炎症に効果がある証拠ですね。
インドのアユールベータでも、歯を丈夫にして、口内炎などの治療に用いられたといわれています。
何だか、ゴマにはとっても体によい成分が入っていそうですね。
次回もゴマのことについて書きます。
ゴマの活性成分セサミン
2007年08月29日
ゴマの力(2)
こんにちは
 水溶性の素材と脂溶性の素材
水溶性の素材と脂溶性の素材
健康食品の素材、言い換えれば活性成分には、
水に溶けるもの(水溶性)と水に溶けにくいもの(脂溶性)とがあります。
これは活性物質の物性によります。
例えば、アントシアニンやビタミンCは水溶性ですし、
CoQ10やビタミンEは脂溶性です。
ゴマの活性成分は後者です。
どちらが良いかは、もちろん一概に言えません。
ただ、最終製品への加工性の良さから、
水溶性の方が好まれる傾向にあります。
しかし脂溶性物質も、最近の製剤加工技術の向上によって、
非常に扱いやすい形状の健康食品として摂ることが出来るようになりました。
ゴマは5000年以前も前から、エジプトで食されてきた長い歴史、食経験があります。だから、非常に安全な食べ物だといえます。
日本へは、6世紀頃、持ち込まれたといわれ、菜種よりも古くから栽培されてきました。ただ、当時は灯油として使用されていました。食用に供されるようになったのは平安時代からだと言われています。
現在は、中国、インド、メキシコ、アメリカ、中南米で盛んに栽培されています。
次回もゴマのことについて書きます。
ゴマの活性成分セサミン
2007年08月28日
ゴマの力(1)
こんにちは
 抗酸化作用
抗酸化作用
多くの健康食品の製品が出回っていますが、その多くの製品に含まれる活性成分について、よく耳にする働き、というか、機能があります。
それは何でしょうか。
それは、抗酸化作用、ということです。
その健康食品に含まれている活性成分の抗酸化作用が高い、
ということですが、
これは、言い換えますと、
その活性成分自体は、「非常に酸化され易い」ということになります。
つまり自らは酸化を受けて、周りの物質や組織を守る、ということになりますね。
最近の研究では、
人体組織の酸化によって老化が進行し、
また発癌が起こりやすくなる原因にもなっている、
と言われています。
そこで、有害な酸素や過酸化物から身を守るために、
「抗酸化剤」の摂取が重要と言われています。
ゴマには強い抗酸化作用があります。
次回もゴマのことについて書きます。
ゴマの活性成分セサミン
2007年08月23日
機能性食品素材のご案内(5)
こんにちは
 特定保健用食品
特定保健用食品
数多くの健康食品が出回る中、その栄養強調表示ができるのは、「特定保健用食品」だけで、この制度は米国のDSHEA法と並んで注目されています。この「特定保健用食品」として認められるためには、生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関して、薬事・食品衛生審議会で個別審査がなされ、総合的に適正と認められ、厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。
許認可を受けるための基本的な要件は、以下の8項目になります。
1) 食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できるものであること。
2) 食品又は関与成分について、表示しようとする保健の用途に係る科学的根拠が医学的、栄養学的に明らかにされていること。
3) 食品又は関与成分についての適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるものであること。
4) 食品又は関与成分が添付資料等からみて安全なものであること。
5) 関与成分について、次の事項が明らかにされていること。ただし、合理的理由がある場合は、この限りでない。
ア 物理学的、化学的及び生物学的性状並びにその試験方法
イ 訂正及び定量試験方法
6) 同種の食品が一般に含有している栄養成分の組成を著しく損なったものでないこと。
7) まれにしか食されないものでなく、日常的に食される食品であること。
8) 食品又は関与成分が、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日付薬発第476号厚生省薬務局長通知)の別紙「医薬品の範囲に関する基準」の別添2「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に含まれるものでないこと。
「特定保健用食品」表示義務があります。
1) 特定保健用食品である旨(条件付き特定保健用食品にあっては、条件付き特定保健用食品である旨)
2) 許可又は承認を受けた表示の内容→添付文書への記載でも可
3) 栄養成分量及び熱量
4) 原材料の名称
5) 内容量
6) 1日当たりの摂取目安量
7) 摂取の方法及び摂取する上での注意事項
8) 1日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示する成分の栄養素等表示基準値に占める割合 (栄養素等表示基準値が定められているものに限る)
9) 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものはその注意事項
10) 許可又は承認証票
11) その他
労働厚生省のサイトには、特定保健用食品の既許可リストがありましたが、現在はアクセスができない状態になっています。これまでに認められた食品のカテゴリは次のようになります。
1) お腹の調子を整える食品
2) 血圧が高めの方に適する食品
3) コレステロールが高めの方に適する食品
4) 血糖値が気になる方に適する食品
5) ミネラルの吸収を助ける食品
6) 食後の血中の中性脂肪を抑える食品
7) 虫歯の原因になりにくい食品
8) 歯の健康維持に役立つ食品
9) 体脂肪がつきにくい食品
10) 骨の健康が気になる方に適する食品
次回から、売れ筋の健康食品のレビューをおこないます。
2007年08月16日
機能性食品素材のご案内(4)
こんにちは
 健康食品との上手な付き合い方
健康食品との上手な付き合い方
健康食品を摂ろうと思われるときは、健康ともいえないけれど病気までは至っていない状態のとき、あるいは季節的に、または一定の条件のもとでよく起こる症状がでたとき、などではないかと思います。これに対して明らかな疾病の場合には、言うまでも無く、直ちに医師に相談すべきです。
一般的に、例えば、がん、アトピー、認知症などの難病に対しての効果をうたっている健康食品には少し注意が必要です。また、最近は少なくなったようですが包装や箱の印刷が華美なものの中には、品質的に満足できないものが多かったと聞いています。このブログでは健康食品をレビューし、効果が証明された製品をご紹介していきたいと思っています。
健康食品の中には効果が出るのに時間がかかるものもありますので、通常、三週間程度服用し、効果が認められなかったならば、服用をやめるべきだと考えられています。その健康食品自体が効かないのか、或いは、全く違う原因によることが考えられるからです。
特に生薬・ハーブ系の健康食品の中の成分には、副作用もあります。量の問題もありますが、症状が悪化すれば、服用は直ちにやめるべきです。また、現在服用している医薬品との相互作用、複数の健康食品の同時服用による相互作用もありますので、何らか悪化に向かう変化を感じたら、服用をやめ、医師に相談すべきです。
健康の基本になるのは、やはりバランスのとれた適量の食事と適度の運動、充分な睡眠などです。健康食品は、あくまでも補助的な位置づけです。この点を忘れないようにしましょう。
2007年08月15日
機能性食品素材のご案内(3)
こんにちは
 健康食品の問題点
健康食品の問題点
健康食品と称される製品は、色々な方法でつくられています。
例えば、
- 特定の食品を加工して製したもの
- 食品中の特定の成分を抽出して製したもの
- ハーブ、生薬系植物を抽出して製したもの
- 合成や発酵によって製したもの
- 昆虫類の粉末を製したもの
などです。
特定の機能性を狙っていろいろな商品をつくるのですが、基本的には、例えば植物エキス製品の場合、日本では医薬品に分類されていない、基原植物(原料になる植物)に関して食経験がある、といった内容でひとまずOKとなります。
エキス製品の場合、地球上のどこかに食経験があっても、馴染みのない植物から抽出して製した製品を摂取するのは、少し不安です。それに特定の成分の含量が高くなるように、製したわけですから、食品としては、もともとあったバランスを欠いているようにも思えてきます。
かって心臓疾患治療薬であったCoQ10は、現在は発酵法でつくられますが、摂取量に上限はあるのでしょうか。医薬品であったときには、しっかりとした投与上限がありました。
また、妊婦などに対する影響、現在服用している薬との相互作用も、完全に解明されているのでしょうか。
それで最近は、確かな最終製品メーカーが安全性としっかりとしたバックデータがある有効性に重点をおいて素材を選ぶようになりました。こうした点を踏まえ、よい健康食品をご紹介して行こう思います。
2007年08月14日
機能性食品素材のご案内(2)
こんにちは
 健康食品
健康食品
特定保健用食品(いわゆる、トクホ)、栄養機能食品および特別用途食品には、その健康効果の表示に関して、薬事法、食品衛生法等の規制があります。
しかし、医薬品ではない、「その他の健康食品」には、農薬、有機溶媒、重金属等の有害な物質の混入がない限り、規制される対象とはなっていません。
この「その他の健康食品」の市場は、数千億円といわれるほど大きなもので、どんな製品を入手すべきか、判断し難いという実情があります。
このブログでは、「その他の健康食品」の代表的ものについて、もとになっている機能性食品素材をみることによって簡単に説明し、推奨される製品をご紹介したいと思います。